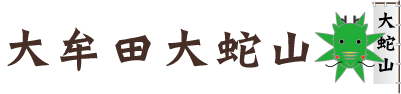







おおむたナビは大牟田観光協会が運営する大牟田の公式観光サイトです。
観光、イベント、グルメなどの情報が満載です!
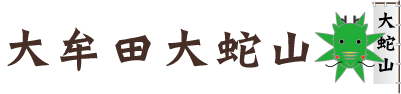






大牟田大蛇山は、江戸時代初期から始まった神社の祭礼(祇園祭)です。
その祇園祭は、京都 八坂神社の祇園会(ぎおんえ)が始まりで、貞観(じょうかん)5年(西暦863年)に当時の疫病流行により、疫病退散と五穀豊穣を願って執り行われました。
神社の他の祭礼は、春の「豊作を祈願する祭」と、秋の「豊作を感謝する祭」との春・秋の祭礼ですが、暑さの一番厳しい旧暦6月(7月)に斎行されるのが祇園祭です。
毎年、大牟田大蛇山祇園も六山を中心に神事を行い、神振行事としての大蛇山巡行を行っています。
六山の各神社では神事を厳かに斎行し、各山ごとに疫病退散と五穀豊穣の願いを込め、それぞれの諸事が執り行われます。
さて、大牟田大蛇山のはじまりは、寛永17年(1640)に三池に祇園宮が祀られて以後とされ、嘉永5年(1852)には、本山と呼ばれる山車があり、大蛇を作る材料(竹・藁・和紙)・花火の材料(焔硝・硫黄)等が必要と古文書に記されていますので、約380年前と考えられています。
大蛇山は、花火や鐘・太鼓を使用する等、京都や九州各地の祇園祭とは少し趣が違います。これは、この地方独特の水神・龍神信仰が重なり発展したと思われます。
古くは、三池本町 新町の二山、そして本町筋の本宮・二区・三区・諏訪の四山と合わせて六山の祇園祭が「大牟田祇園さん」と呼ばれていますが、近隣地区(江の浦・大和町中島・南関町等)にも大蛇祇園祭があります。
大牟田市の夏まつり“おおむた「大蛇山」まつり”が、7月の第4土日に開催されており、初日に祇園六山の神事として巡行・競演・御止・かませが行われています。大牟田市内の各地域にも大蛇山が作られ、2日目の大蛇山大集合に、現在 12基の大蛇山が参加しています。
以前は、祭の最後に勇壮な「山崩し」と「目玉取り」が繰り広げられました。「左右」と云うように、古来より日本では、左が上位とされ、左目が縁起のよいものとされていましたが、近年は安全に注意して子供たちによる「山崩し」が行われています。大蛇の一部を縁起物として家に持ち帰ると、無病息災・家内安全・幸福(しあわせ)になると信じられています。
また、大蛇の口に子供を入れると(「かませ」と云う)健康に育つと云い伝えられていて、市内外の各地より健康を願った多くの親子が「かませ」ご祈願に列をなします。
三池藩大蛇山(新町)と三池祇園宮(本町)の二つからなる三池の大蛇山は、同市の夏まつり「大蛇山」の六山の中で最も歴史が古いとされているため、大牟田市は平成22年4月14日無形民俗文化財に「三池の大蛇山」を指定しました。






三池地方に伝わる「ツガネと大蛇の物語」は、水神信仰が古くからあったと思われます。
蛇や龍を水の神の象徴とする水神信仰、祭神を悪病よけや農業の神とする「祇園」、農業に関係するこれらの信仰が絡み合い、祇園のお祭りに大蛇が取り入れられ「大蛇山」ができたと考えられます。
ギリギリ人間に見える姿に変化(へんげ)した大蛇の化身。炭鉱のまちの人々からもらったつるはしとヘルメットがお気に入り。まちの守り神なのだと言い張るが、その真相は定かではない。
ジャー坊のシール・ボールペン・メモ帳・アクリルキーホルダー・うちわ・缶バッジ・タオル・皿・湯呑・マグカップ・ゴルフカバー等


